弁理士の日記念ブログ企画2025に参加、ということで、今年のテーマは「生成AIと知財業界」ですので、一特許翻訳者として、2025年7月現在、どのような使い方をしているのかを、書ける範囲で書いていこうと思います。
なお、前提として、取引先との間で「生成AIの使用が禁止」と明言されている事項に対しては、生成AIを使うべきではありません(出願審査請求前の書面の、翻訳補助など)。しかし一方で、公開公報や、外国書面出願のための翻訳書類の原文(Google patentで検索してヒットする公報など)は、公開情報ですので、極端なことを言うと、「この文章を翻訳して」という風に生成AIを使うことは許容されるかと思います。
なお、この記事を書いている時点で、私が使っている生成AIがChatGPTの4oだけのため、以下では、生成AIを指す意味で「ChatGPT」という表現を使っていますが、固有名詞の意味合いに限定する意図はないので、皆さまがお使いの生成AI全般を指す、と読み替えてもらって差し支えありません。
①メールの返信に使う
生成AIを一番重宝しているのは、実はメールの返信の作成かもしれません。
これは、私が英日翻訳をしていて、取引先のほとんどが海外(英語でのやりとり)という事情が関係していると思うのですが、英語のメールの返信をタイピングでやっていると、時間がいくらあっても足りません(細かい文法のミスを気にしたり、どういう風に文章を書けば良いか、などで、案外時間が取られてしまいます)。
また、脳のメモリを食ってしまう、面倒くさいやりとり(交渉事など)も、仕事(翻訳)に支障が出てしまうので、これもChatGPTに任せてしまうことが多いです。
ここでは、超大雑把なプロンプトを書くに留めますが、「(相手のメール)に対して、返信を作ってください。Aという内容と、Bという内容と、Cという内容を含めてください。プロフェッショナルな文面にしてください」というような感じで、とにかく英文の出力を即興でやってもらっています。
自分に限った話ではないと思いますが、生成AIの出力スピードは超絶速いので、「こういうことを盛り込んでほしい」ということを伝えたら(しかも日本語で)、それをそのまま英語で上手くまとめて出力してくれるので、こういう庶務には、生成AIを活用するに越したことはないと思います。
②技術の基本原理の理解
私は、翻訳そのものをChatGPTにしてもらうことは基本なくて(例外があるのですが、それは③で後述)、その理由は、「生成AIを使うよりも、翻訳ソフトで用語集とメモリを使ったほうがスムーズにできるから」というものなのですが、ChatGPTには、明細書に出てきた、馴染みの浅い分野の用語の解説などをしてもらうことは多くなりました。
例えば、化合物の分析を行うにあたり、X線回折を使う方法が説明されている場合に、X線回折とはなんぞや、ということを、ChatGPTに聞いたりします。もう少し具体的に書けば、「X線回折に出てくる”2θ”とは何ですか? 三角関数でθは出てきますが、なぜ2倍になるのですか?」みたいな(読む人が読んだら笑われてしまいそうな内容だと思いますが)内容で質問をします。
すると、ChatGPTは親切なので、
・X線回折は何を分析する手法か
・どんな時に使うのか
・どんな原理か
・2θとは
・なぜ2θを使うのか
ということを、ある程度ストーリーを持たせて説明してくれます。
今までは、専門サイトを読んで、自分の理解度とサイトの説明の間にある基本知識の差を、埋め合わせられないままなんとなく理解した感じで終わっていたのが、ChatGPTを使うことで、以前よりも少しは深く理解出来た感じになりました(ここでも、「感じに」なので、根本的に理解出来ているかどうかと言えばあやしいですが)。
私は、物理分野にそこそこ抵抗があるので(結晶格子とかラマン分光とか、光を当てるとか音がどうとか波がどうとか力学とか、こういう分野が結構苦手)、その説明を分かりやすくしてもらって、とりあえず明細書を翻訳するのに足りる程度の理解を、即興で出来るようにするには有効な使い方だと思います。
※理屈だけ言えば、ChatGPTを使ったら、あらゆる物理原則、分析手法について、分かりやすく説明してもらって、理解度を深めることは可能ですね。
③生成AIが得意な部分の翻訳だけをスポットで任せる
私の場合、翻訳ソフトを使うよりも、生成AIに翻訳してもらうほうが便利な場合が(現時点では)1つだけあって、そこでは、生成AIを翻訳自体に使っています。
それは、「長い化合物の翻訳」です。
製薬系の明細書などで、立体異性体を含む、超絶長い化合物の翻訳が必要な場合がありますが、これは、翻訳ソフトを使って翻訳しようとすると、(理由は述べませんが)結構面倒です。
ですが、生成AIを使って、例えば以下のようなプロンプト(ざっくり)を打ち込んで、「この化合物を翻訳して」と入力すると、手動で翻訳するよりも早く翻訳ができてしまいます。
プロンプトの例)
・数字もハイフンもコンマも、全て全角で出力して
・原文にスペースがある場合、それは訳文では削除して
・化合物(官能基)の説明は不要、ただ翻訳だけして
生成AIの良い所は、最初に打ち込んだプロンプトの出力を見て、ブラッシュアップしていけることなので、場合によってはさらに、
・”XXX”という化合物の訳は「●●●」(化合物命名法に沿ったもの/日本で慣用的に使われているもの)にしてください
・”YYY”という化合物の訳は、「▲▲▲」が正しいです
のように、フィードバックループを構築することで、より正確な生成が可能になります。
翻訳のワード計算は単語ベースなので、どれだけ化合物名が長くても1ワードと数えられる場合が多い(MS wordや、各種翻訳ソフトによって異なる場合あり)のと、目視+登録している用語データで手動で進めていくと、どこかで抜け漏れを起こす可能性がなきにしもあらずなので、こういう場合には、生成AIを使ってワンポイントで翻訳を補助してもらうのはありだと思います。
まとめ
以上、一翻訳者として、「生成AIと知財業界」というテーマで記事を書かせてもらいました。
もともと、生成AIには色々と抵抗があったのですが、自分なりの有効活用法を見つけ出してから、使いようによっては尋常でない武器になるなと気付きました。今後も機会があれば、最新の活用方法についてまとめられればと思います。
スポンサードリンク
jiyuugatanookite.com
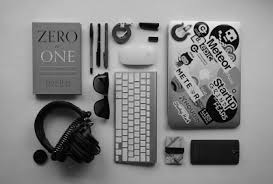

コメント